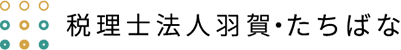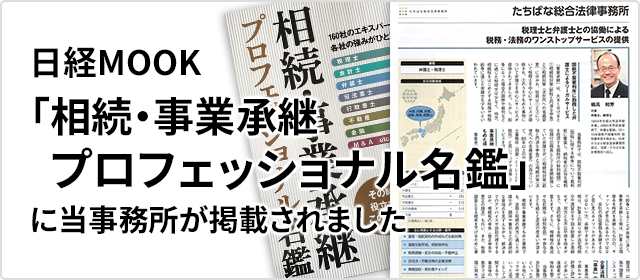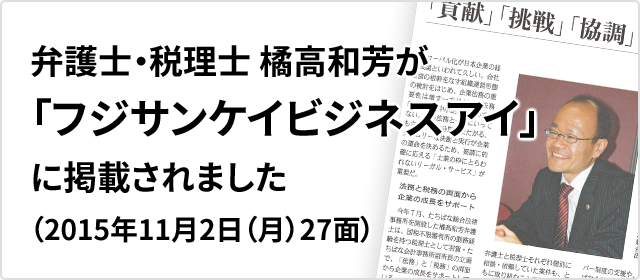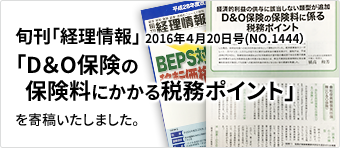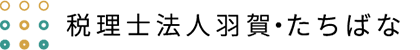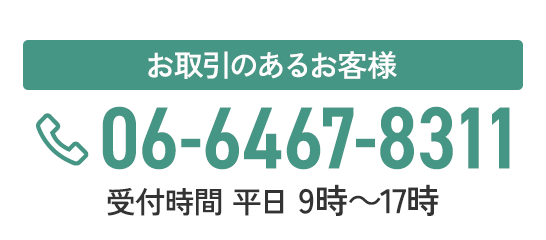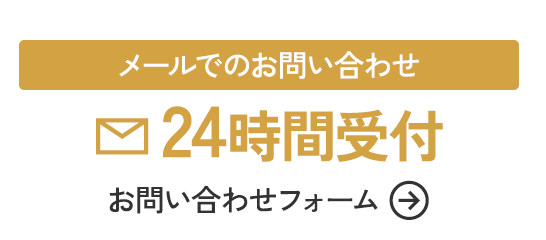相続税の脱税で後悔しないために!基礎知識から刑事罰まで
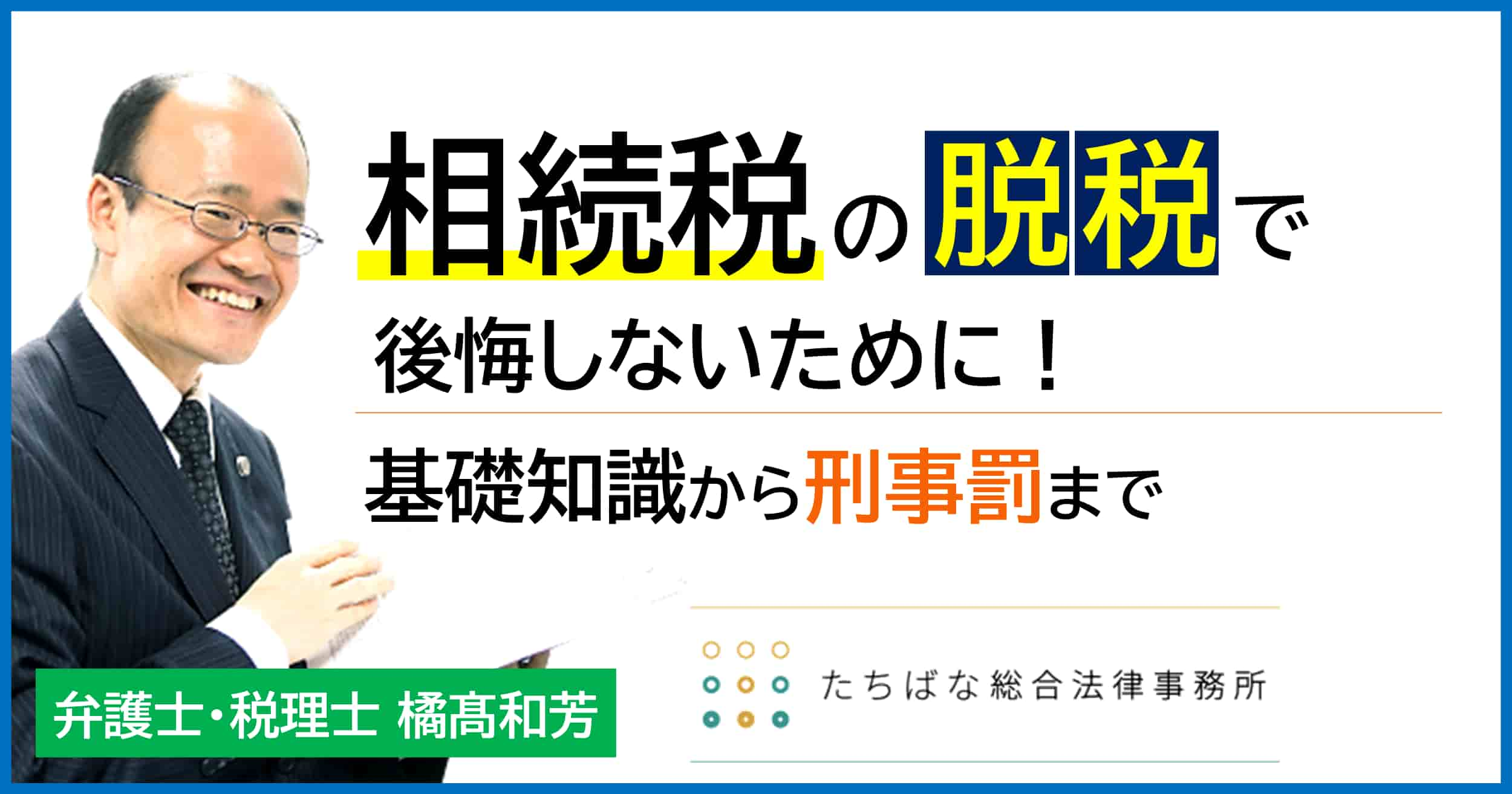
執筆者情報 [開く]
このコラムの要点(目次)
相続税の脱税で後悔しないために!基礎知識から刑事罰まで
相続税の申告は重要な手続きですが、財産評価や法律の知識不足が意図せぬ申告漏れにつながることがあります。
納税額を減らしたいという思いも、方法を誤れば「節税」ではなく「脱税」とみなされ、深刻な事態を招きます。
相続税の脱税は、意図的な財産隠しだけでなく、知識不足が原因で生じることも少なくありません。
例えば、「家族名義の口座だから申告不要」「タンス預金ならバレない」といった誤った自己判断が、申告漏れにつながるケースです。
法定控除や特例を正しく理解し、適切な対応を行うことが、家族と財産を守るために何より重要です。
本記事では、法律の専門家として、相続税の基礎知識、「脱税」と「節税」の明確な違い、脱税発覚時の重いペナルティ(罰則)や時効まで詳しく解説します。
安心して相続手続きを進めるための正しい知識を得て、大切な財産を守る参考にしてください。
1. 相続税とは?申告が必要となる条件と基本ルール
相続税の基本的な仕組みと申告ルールを理解することは、脱税リスクを避ける第一歩です。
相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を承継した人(相続人など)に対して課される税金です。
土地や建物(不動産)、預貯金に加え、株式などの金融資産も課税対象となります。
課税対象となる財産の合計額(遺産総額)から、後述する「基礎控除」が差し引かれ、その残額(課税遺産総額)に対して税率が適用されます。
相続税の申告が必要な人の割合は、実はそれほど多くありません。
国税庁の「令和4年分 相続税の申告事績の概要」によると、令和4年(2022年)に亡くなった方のうち、相続税の課税対象となった被相続人の数は約15万人、その割合は9.6%でした。
これは、基礎控除の仕組みにより、財産総額が一定額以下の場合には相続税がかからず、申告自体が不要となるケースが多いためです。
しかし、正確な財産評価を怠ると、「申告は不要だと思っていた」が実際は基礎控除を超えていたり、「本来かからないはずの税金を余計に支払ったり」、逆に申告漏れを起こして後で指摘を受けたりと、大きな後悔につながる可能性があります。
財産の算定や控除の活用は、相続税の根幹にあたる重要なポイントです。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内です。
申告書を税務署に提出し、納付を完了する必要があります(相続税法第27条)。
見過ごしやすい細部に注意しながら期限を守ることが、余計なペナルティを回避するうえで欠かせません。
1-1. 相続税の基礎控除と課税対象
相続税の計算で最初に考慮するのが基礎控除です。
基礎控除額は、以下の計算式で算出されます(相続税法第15条)。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、基礎控除額は 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 です。
遺産総額がこの額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。
課税対象となる財産は、預貯金や株式、不動産など一般的な財産だけではありません。
以下の「みなし相続財産」なども課税対象に含まれる点に注意が必要です。
- 死亡保険金(生命保険金)
- 死亡退職金
- 被相続人の死亡前3年~7年以内に贈与された財産
※令和6年(2024年)1月1日以後に行われた贈与より、生前贈与加算の期間が段階的に3年から7年に延長されます。 - 相続時精算課税制度を適用した贈与財産
ただし、死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円 × 法定相続人の人数」までの非課税枠が設けられています(相続税法第12条)。
これらを活用することは合法的な「節税」となります。
基礎控除を超える部分があるかどうかを判断するには、被相続人の残した財産をもれなく把握し、適正に評価する必要があります。
たとえば、タンス預金を見落とすことも申告漏れにつながります。
また、財産評価のルールは複雑で、特に不動産評価では路線価や固定資産税評価額など多角的な指標を考慮します。
ご自身で判断しにくい場合は、相続税に強い税理士などの専門家に相談し、適切な評価を受けることをおすすめします。
1-2. 申告と納税期限の流れ
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に行う必要があります。
重要な点として、遺産分割協議が10か月以内に終わっていない場合でも、申告期限は延長されません。
その場合は、法定相続分で分割したものとして仮の申告と納税を行い、後に協議がまとまった段階で修正申告や更正の請求を行う必要があります。
複数の相続人がいる場合、正確な情報共有が必須です。
相続人それぞれが単独で相続税申告をすることは可能ですが、申告の数字に違いがあると、後日、税務署からの調査を受ける可能性が高くなります。
結果として、後述する「加算税」や「延滞税」など、余計なコストが発生するリスクを高めます。
相続税の納税は、原則として現金で一括払いです。
しかし、財産状況(例:遺産の大半が不動産で現金が少ないなど)によっては、延納(分割払い)や物納(不動産などで納付)の制度を利用できる場合もあります。
早めに相続手続きの全体像を把握し、必要に応じて計画的な資金準備を行うことが、スムーズな納税への近道です。
2. 相続税の脱税とは?節税との違いを理解しよう
合法的な「節税」と、税務当局が厳しく追及する違法な「脱税」には、法律上明確な境界線があります。
- 節税
法律(租税法)が認めている範囲内で、控除や特例を適切に活用し課税額を抑える正当な権利です。 - 脱税
意図的に事実を隠蔽したり、虚偽の申告をしたりするなど、不正な方法で納税を回避する違法行為(犯罪)です。
相続財産を正しく評価し、所定の手続きを守っていれば、たとえ納税額がゼロになったとしても何ら問題にはなりません。
しかし、控除の適用や財産評価に関する理解が不十分だと、意図せずとも結果的に法を逸脱してしまう事例がある点は要注意です。
例えば、不動産会社や金融機関からのアドバイスが、税務上の観点からは誤っていたとしても、申告の責任は納税者自身に及びます。
節税と脱税を混同してしまうと、重い追徴課税や刑事罰につながるだけでなく、家族間で「知っていた」「知らなかった」といった不要なトラブルが起こる可能性も高まります。
専門家のサポートを活用し、ルールに沿った対策を行うことが大切です。
2-1. 不正行為として扱われるケース
相続税の代表的な不正行為(脱税)には、財産隠しや明らかな虚偽申告などがあります。
具体的には、以下のような行為が典型例です。
- 名義預金の不記載(被相続人が実質的に管理していた家族名義の口座を隠す)
- タンス預金(被相続人が自宅で保管していた現金)を申告しない
- 被相続人が亡くなる直前に預金を引き出し、それを申告せずに隠す
- 海外口座や暗号資産(仮想通貨)を申告しない
- 不動産の評価額を意図的に低く偽って申告する
- 架空の借入金(債務)を計上する
これらは税務署の調査で比較的発覚しやすく、発覚した場合は最も重いペナルティである「重加算税」(後述)や、悪質な場合は刑事罰の対象となるリスクが非常に高い行為です。
相続税は自己申告制(申告納税方式)のため、意図的な隠ぺい行為が可能に見えます。
しかし、後述の通り、銀行口座や不動産移転情報、さらには過去の所得情報などは国税庁のシステム(KSKシステム)を通じて徹底的に監視されており、「バレないだろう」という考えは極めて危険です。
2-2. 合法的な節税と脱税はどこが違う?
合法的な「節税」と違法な「脱税」は、その手段の正当性によって明確に区別されます。
【合法的な節税策(例)】
節税は、相続税法や租税特別措置法などで制度として用意された控除や優遇措置を適切に利用し、法的に認められた範囲で納税額を減らす手段です。
- 生前贈与の活用
✔ 暦年贈与(年間110万円の基礎控除枠)の活用
✔ 相続時精算課税制度の選択
✔ 贈与税の配偶者控除(居住用財産)の特例の利用 - 生命保険の非課税枠の活用
✔ 「500万円 × 法定相続人の人数」の非課税枠を最大限利用する - 小規模宅地等の特例の活用
✔ 被相続人の自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額する - 配偶者の税額軽減の活用
✔ 配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円までは相続税がかからない制度
これらの節税策を生前から計画的に行うことは、賢明な相続税対策です。
【違法な脱税行為(例)】
いっぽうで、脱税とは制度を悪用したり、事実を偽ったりして、実際の資産を過少に報告する手段です。
- 財産の隠蔽
タンス預金や名義預金、海外口座を意図的に申告しない。 - 財産の過小評価
不動産の評価額を意図的に時価より著しく低く操作する。 - 事実の仮装
実際には贈与していないのに贈与契約書を偽造する、架空の借用書を作成する。
節税と脱税の決定的な違いは「意図的な隠蔽・仮装」の有無と「法律上の正当性」です。
財産の開示を正しく行い、税法に準拠しているかどうかが決定的な分かれ目です。
3. 相続税の脱税につながる主なケース
相続税の脱税に共通するのは、「税務署にバレないだろう」という安易な考えと、故意に財産を隠そうとする点です。
脱税の主なケースとして、名義変更や預金・不動産の過少申告が挙げられます。
特にタンス預金や海外口座は把握が難しいと思われがちですが、近年は情報網が広がり、実際には多くのケースで追及を受けています。
不正行為は、多額の重加算税や刑事罰のリスクを増大させます。発覚時のダメージは非常に大きく、故人の名誉だけでなく、相続人同士の関係にも深刻な亀裂を生みます。
節税策は重要ですが、違法スレスレの手法は得策ではありません。長期的にみれば、正しい知識での申告が家族と財産を守る近道です。
3-1. 名義預金・タンス預金の不記載
名義預金とは、実際の所有者は被相続人であるにもかかわらず、名義だけを配偶者、子、孫などの親族に変更している預金を指します。
例えば、「妻(名義人)は専業主婦で収入がないはずなのに、多額の預金口座がある」「子供(名義人)が知らない間に、被相続人がその口座の印鑑や通帳を管理し、入金していた」といったケースです。
こうした口座は書類の上では別の人の所有物と見えますが、税務上は「名義を借りているだけの実質的な被相続人の財産」とみなされ、相続財産として申告する義務があります。
税務署は、後述するKSKシステムや金融機関への調査権限に基づき、口座の入出金履歴や使用状況(誰が通帳・印鑑を管理していたか)を徹底的に調べ、実質的な所有者を判断します。
名義人が口座の存在を知らなかったり、自由に引き出せない状態だったりすると、名義預金と認定される可能性が極めて高いです。
タンス預金の不記載も典型的な脱税手段です。
現金は記録が残りにくいため軽視されがちですが、被相続人の死亡直前直後に引き出された大金や、相続人の収入に見合わない生活実態などから、税務署はタンス預金の存在を推測します。
【名義預金の典型例】
1. 被相続人が父親で、相続人が子であり、別居していたという事例です。
父親宅(箪笥の奥)から父親名義ではない通帳(子名義のみならず別姓名義に通帳も含む)が発見されました。
相続人息子に確認したところ、知らないと回答。その後に息子宅が調査されたところ、同通帳の印鑑届と同じ印鑑や当該別姓名義の印鑑(通帳の印鑑届と合致)したものが発見されました。
その後当該息子は意図的に相続財産から除外していたこと自白しました。
2.当初申告が被相続人のこれまでの収入に比して過少であったため、調査が開始された事例です。
銀行調査を経て極めて多額の相続開始前出金が確認できた。このことを相続人妻からに確認すると、相続人子が勝手に引き出しているとの申告がありました(同妻は当該子を横領の被疑者として警察に被害届を提出)。
そこで、同人及び警察の担当者とともに当該銀行のATMに係る防犯カメラの映像を当該銀行の支店にてチェックしたところ、当該防犯カメラの映像には、当該妻本人が映っていました。
当該妻に対しそのことを確認すると、顧問税理士を通じて、意図的に出金を行い、相続財産から除外していたことを認めました。
3-2. 海外口座を利用した資産隠し
国外の銀行に資産を移すこと自体は、正当な手続きの範囲であれば違法ではありません。
しかし、その事実を申告せずに相続財産として計上しない場合は、悪質な脱税行為とみなされます。
海外口座は日本国税庁が捉えにくいと思われがちですが、それは過去の話です。
今では「共通報告基準(CRS)」など、各国税務当局が金融口座情報を自動的に交換する国際的な仕組みが整備されています。
これにより、日本の税務当局は、日本居住者が海外に持つ口座情報を(協定を結んでいる国・地域からは)自動的に入手できる体制になっています。
多額の入出金や長期にわたって利用されていなかった口座などは重点的に調査の対象となります。
また、資産を海外へ移す段階で為替手数料や国内口座からの送金記録が残るため、完全に痕跡を消すことは困難です。
法令に違反して隠し続けようとするリスクはますます高まっています。
3-3. 不動産評価の過小申告
相続において不動産は資産価値が大きいため、評価額を意図的に低く見せようとする手口があとを絶ちません。
相続税の不動産評価は、原則として時価(実勢価格)ではなく、財産評価基本通達に基づき、土地は「路線価」や「倍率方式」、建物は「固定資産税評価額」を基に計算します。
しかし、例えば「利用価値が著しく低い」として不当に評価額を減額したり、借地権や借家権などの権利関係を偽って評価を下げようとしたりするケースがあります。
税務署は、近隣の取引事例や現地の状況(実地調査)を把握しており、意図的に実勢価格より極端に低い金額を算出した場合、調査で不審点とみなされるリスクが高まります。
特に、相続後すぐにその不動産を売却した場合、申告した評価額と実際の売買価格が明確に記録として残るため、過小申告していた事実が容易に発覚します。
結果として追徴課税や罰則の対象となり、手放す資金が膨大になる恐れがあります。
3-4. 寄付や贈与と偽った資金の移動
被相続人の死亡直前に、寄付や贈与を装って財産を移転し、相続の対象財産を少なく見せる方法がとられることがあります。
特に死亡直前に大きな額を贈与した場合、税務署は「相続税対策のための駆け込み贈与」ではないかと疑いを持ちやすく、その贈与の実態(贈与契約書の有無、資金の使途、名義人が自由に使える状態だったか)を詳細に確認されます。
贈与税の非課税枠(暦年贈与110万円など)を利用して計画的に贈与を進めるのは、合法的な節税策の一環です。
しかし、意図的に見せかけの書類(贈与契約書など)を作成し、実際には被相続人がその資金を管理し続けていた場合(=名義預金と同様)は、贈与が成立していないとみなされ、相続財産として課税されます。
悪質な場合は脱税と判断される危険が高いです。
こうした偽装行為が家族間の信頼関係を損なうだけでなく、発覚後には重いペナルティに直面することにもつながります。
4. 税務署の実態:相続税の脱税がバレる仕組み
相続税の脱税は、昔に比べて格段に見破られやすい時代になっています。
その背景には、税務当局による情報収集のデジタル化とネットワーク化があります。
国税庁や税務署は、不動産の所有権移転(登記情報)や銀行の口座情報などを一元管理しており、相続が発生したタイミング(市町村役場からの死亡届情報に基づく)で関連情報を確認します。
税務署は、被相続人や相続人の過去の所得情報や資産状況を、後述する「KSKシステム」で詳細に把握しています。
「被相続人の過去の所得に比べて、申告された相続財産が少なすぎる」といった不審点があれば、調査対象としてピックアップされます。
また、死亡報告書や戸籍情報をきっかけに、相続人の資産構成を洗い出すことも容易になっています。
取引が不自然な場合は、反面調査(取引先金融機関などへの調査)や実地調査(自宅訪問)を実施して詳細を突き止めようとします。
匿名での情報提供フォームや、遺産分割で揉めた親族からの内部通報など、第三者の通報によって脱税が表面化するケースも増えています。
結果的に、相続税の脱税は想像以上に発覚リスクの高い行為です。
4-1. KSKシステムによる口座・収入情報の徹底管理
KSKシステム(国税総合管理システム)とは、国税庁が運用する巨大な納税情報管理データベースです。
これにより、全国の税務署が、個人の過去の確定申告データ(所得、納税額)、財産情報、さらには家族名義の口座情報や不動産取引のデータまでを瞬時に共有・照合できます。
金融機関は、税務署から調査権限(国税通則法に基づく質問検査権)に基づき照会があれば、口座の入出金履歴(過去10年分程度)を開示する義務があります。
KSKシステムと金融機関からの情報を照合すれば、「被相続人の所得から、子供名義の口座に毎年100万円ずつ送金されている(=名義預金の疑い)」「海外の口座へ不自然な送金がある」といった資金の流れが把握されます。
KSKシステムの充実に伴い、昔は見落とされがちだった小口の資金移動や仮想通貨(暗号資産)取引なども検知されるケースが増えています。
些細な不正でも追及される余地があることを理解しておきましょう。
4-2. ヒアリング・反面調査の実例
税務署は、申告書に不審な点があると判断した場合、まず税務調査を行います。
調査には、税務署内で完結する「机上調査」と、担当官が自宅や事務所を訪れる「実地調査」があります。
【税務調査の時期と確率】
- 時期
相続税の税務調査は、申告期限(相続開始から10か月)から約1~2年後の夏から秋にかけて行われることが多いです。
忘れた頃に連絡が来る、というケースが典型的です。 - 確率
国税庁の発表(令和4年事務年度)によれば、相続税の実地調査の件数は8,196件でした。
申告件数(約15万件)に対する割合は高くありませんが、調査対象に選ばれやすいケース(例:遺産総額が数億円以上と高額、申告内容に不備や矛盾が多い、過去の所得と比較して資産が少ない等)は存在します。
【実地調査の流れ】
実地調査は通常、事前に相続人(または代理人の税理士)に電話で日程調整の事前通知があります。
調査当日は、通常2名程度の調査官が訪問し、1~2日かけてヒアリングや資料の確認が行われます。
【ヒアリング・反面調査の実例】
調査官は、申告した相続人への直接調査だけでなく、相続に関わりのある第三者(金融機関、取引先、親族)に対しても反面調査を行います。
- ヒアリングでよくある質問
✔「被相続人の生前の趣味や生活の様子はどうでしたか?」
✔ 「タンス預金やへそくりなどはありませんでしたか?」
✔ 「ご家族名義の通帳や印鑑は、どなたが管理されていましたか?」 - 調査される資料
✔ 預金通帳(被相続人および相続人全員分。過去5~10年分)
✔ 金庫、仏壇、机の引き出しの中(現物確認)
✔ 日記、手紙、エンディングノート
法人や取引先との資金のやり取りが見られる場合には、取引明細を引き出して整合性をチェックします。
愛人や別居している家族の口座が絡んでいるケースなども調査の対象となります。
こうした多角的な手法によって、故意に隠した財産や虚偽の報告は意外と早い段階で明るみに出やすいです。
必要以上に調査を長引かせないためにも、初めから正直な申告を心がけるべきです。
相続税調査では、銀行預金が重要視されることが多いです。
特に、ご高齢の被相続人は行動範囲が狭くなりがちなため、多くの金融機関に口座があるのに、近隣の銀行口座が申告されていない場合、税務署はその口座の存在を調べることがあります。
また、多くの方が利用しているゆうちょ銀行の口座がない場合も、調査のきっかけになることがあります。
4-3. 情報提供フォームや第三者からの通報
国税庁はウェブサイト上で匿名の情報提供フォームを開設しており、不正が疑われる人物や法人を通報できる仕組みを整えています。
また、相続をきっかけに、遺産分割で揉めた親族や、被相続人の内情を知る関係者が「あの人(相続人)は財産を隠している」と税務署に内部告発(通報)することも少なくありません。
トラブルを未然に避けるためにも、財産の分割や税金の負担について家族と十分に話し合い、合意形成を図っておくことが重要です。
後から隠されていた偽装行為が発覚した場合、家族内で深刻な信頼問題が起こります。
第三者通報が入れば税務署の注意が一気に集中し、徹底的に調べられる可能性があります。
不正があると判断されれば、高率な追徴課税だけでなく刑事告発につながるケースもあるため十分なリスク認識が必要です。
5. 相続税脱税が発覚した場合のペナルティ・罰則
相続税の申告漏れや虚偽の申告(脱税)が税務署の調査で見つかると、本来納めるべき税金(本税)の追徴に加えて、重いペナルティ(附帯税)が科されます。
相続税における脱税が税務署の調査によって明るみに出ると、「加算税」などの追徴課税が課されます。
これは申告内容の不備の程度や悪質性によって、税率が上乗せされる仕組みです。
支払うべき相続税だけでなく、複数のペナルティが合わせて課されるケースもあります。結果的に当初よりも相当に大きな金銭的負担がのしかかることになります。
さらに、悪質と見なされれば刑事告発される場合もあり、罰金もしくは懲役といった厳しい刑事罰が下されます。
家族の財産を守るはずが、一度の不正行為で大きな代償を払う事態に陥るリスクがあります。
5-1. 過少申告加算税・無申告加算税
【過少申告加算税】(国税通則法第65条)
これは、申告書を期限内に提出したものの、記載された税額が実際よりも少なかった場合(申告漏れ)に課されるペナルティです。
- 税率
原則として、追加で納めることになった税額の10%
(追加税額が当初の申告税額または50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
ただし、税務調査の事前通知を受ける前に、自主的に「修正申告」を行えば、この過少申告加算税は課されません。
調査通知後であっても、実地調査で指摘を受ける前に修正申告すれば、税率が軽減される余地があります(5%または10%)。
【無申告加算税】(国税通則法第66条)
これは、申告期限(10か月)までに相続税の申告をまったくしなかった場合に課されるペナルティです。
- 税率
原則として、納めるべき税額に対し15%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)
(税務調査の事前通知後に「期限後申告」した場合は軽減されますが、税率は高めです)
もし、税務調査の通知を受ける前に、自主的に「期限後申告」をすれば、税率は5%に大幅に軽減される余地があります。
「申告を忘れていた」と気づいた場合は、1日でも早く自主的に申告することが重要です。
どちらの加算税も余計な出費に直結します。期限内に誠実な申告を行うことが賢明です。
5-2. 重加算税や延滞税の計算方法
【重加算税】(国税通則法第68条)
これは、ペナルティの中で最も重く、財産の「仮装」や「隠蔽」(=意図的な脱税)があったと認定された場合に課されます。
- 過少申告加算税に代えて課される場合
追加税額の35% - 無申告加算税に代えて課される場合
納付すべき税額の40%
例えば、名義預金やタンス預金を故意に隠していたことが発覚すれば、この重加算税の対象となります。
上記の加算税とは比較にならないほど高率なペナルティです。
【延滞税】(国税通則法第60条)
これは、利息に相当するペナルティで、法定納期限(申告期限と同じ)の翌日から、税金を完納する日までの日数に応じて自動的に課されます。
- 税率
納期限の翌日から2か月を経過する日までは「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方、それ以降は「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。
(※税率は令和の各時期によって変動します。例えば、令和5年中は納期限後2か月までは年2.4%、2か月経過後は年8.7%でした)
申告の遅れや資金不足による支払い遅延のツケは、時間が経つほど延滞税として膨らんでいきます。
5-3. 悪質と判断されると刑事罰も
過度に財産を隠蔽したり、虚偽の手続きを繰り返すなど、極めて悪質と判断された場合は、加算税といった行政処分だけでなく、検察庁に告発され、刑事罰を科される恐れがあります(相続税法第68条)。
- 【相続税法第68条(ほ脱犯)】
偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(免れた税額が千万円を超えるときは、情状により、免れた税額に相当する金額以下の罰金を併科することができる)
これは納税義務違反という範疇を超え、刑法上の罪(犯罪)として問われることを意味します。
刑事罰としては、最長で10年の懲役や1,000万円の罰金(または併科)が科される可能性があります。
個人の信用にも重大な影響を与え、実社会での活動にも懸念が広がります。
仮に多額の追徴課税(重加算税など)を支払い完了しても、悪質とみなされた場合は刑罰を免れないこともあり、一度の脱税で失うものは想像を超えるほど大きいといえます。
6. 相続税の時効と追徴リスク
「申告しないで5年(あるいは7年)逃げ切れば、時効になるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、その考えは極めて危険です。
相続税にも「時効」に似た制度として「除斥期間(じょせききかん)」があります。
これは、一定期間が経過すると国が課税権を行使できなくなるという決まりです(国税通則法第70条)。
税務署は時効前でも不審な取引があれば積極的に調査を行い、追徴課税を進めます。
時効が近づいている場合ほど重点調査の対象になりやすく、突発的な調査で不正が発覚することも考えられます。
悪質性が高いと判断されたケースでは、この期間が通常より長くなります。
時効成立を当てにして財産隠しを行う行為は、リスクを過小評価しています。
現在のKSKシステムや国際的な情報共有体制の下では、何年が経過しても、税務署が重大な不正行為を見逃すことはほぼありません。
時効成立を待つのではなく、対象にならないうちに正しく申告を行うことこそが、唯一のリスク回避手段です。
6-1. 原則5年・悪質な場合は7年
相続税の課税権の除斥期間(時効)は、申告期限(相続開始から10か月後)の翌日から起算されます。
- 原則
申告期限から5年 - 悪質な場合(偽りその他不正の行為があった場合)
申告期限から7年
つまり、申告しなかった場合、最長で相続開始から7年10か月は、税務署から追徴課税を受けるリスクが残り続けることになります。
「7年経てば安心」というわけでもありません。
税務調査は多角的に行われるため、本当に発覚を免れるのは難しいのが実情です。
時効をあてにした隠ぺい行為を行うよりも、早めに税理士などの専門家に相談し、正しい手続き(期限後申告や修正申告)で清算することが、被相続人や相続人双方にとっても精神的・経済的負担の少ない方法です。
6-2. 時効成立までに課せられる追加徴税の可能性
もし時効が成立する前に税務調査が入った場合、脱税が認定されると、本税に加えて、重加算税(最大40%)と、延滞税(最大7年分以上)がまとめて課されます。
特に延滞税は、時間が経つほど膨れ上がるため、時効間際での発覚は、ペナルティの総額が本税を上回るほどの高額な納税を余儀なくされる可能性が高くなります。
特に大型の資産隠しや海外口座の利用が見つかった場合は、逃れる術がないほど徹底的な調査が行われます。
一度疑いが生じると、大掛かりな反面調査に発展するため、精密な裏付けが取られやすいです。
時効ギリギリを意識して隠し通そうとする行為は、むしろさらに厳しい目で見られる傾向にあります。
リスクをとって不正を行うよりも、適正な申告と納税を完了させたほうが結果的に得策です。
7. まとめ:リスクを回避し正しく相続税を申告しよう
相続税の脱税のリスクを知ることは、結果的にご自身とご家族が安心して相続手続きを進めるために不可欠な知識です。
大切なのは、トラブルを未然に防ぐ正確な情報と行動です。
相続税の申告は、頻繁に経験することではないため、知識が不十分なまま進めてしまいがちです。
「これくらいならバレないだろう」という小さな油断が、後に大きなペナルティと後悔につながります。
一つ一つの手続きを丁寧に行い、財産を正しく評価して申告することが何よりも大切です。
万が一、税務署から「相続税についてお尋ねしたい(実地調査の事前通知)」と電話があっても、慌てる必要はありません。
- まずは冷静に、調査の日程や目的を確認します。
- その場で即答せず、「顧問税理士(または弁護士)と相談してから折り返します」と伝え、すぐに専門家へ連絡してください。
税務調査の対応には高度な専門知識とノウハウが要求されます。
専門家が立ち会うことで、調査官の質問の意図を正確に把握し、相続人にとって不利にならないよう、法的な観点から適切に対応することが可能になります。
【今、不安を抱えている方へ】
「もしかしたら申告漏れがあるかもしれない」「申告期限を過ぎてしまった」と不安を抱えている場合でも、手遅れではありません。
税務調査の通知が来る前に、自主的に修正申告や期限後申告を行えば、ペナルティ(加算税)は大幅に軽減されます。
相続税に関する問題は、税務と法律の両面が複雑に絡み合います。
もし不明点や不安がある場合は、相続税に強い税理士や弁護士が在籍する当事務所に早めに相談し、適法な節税策や正しい申告方法のアドバイスを受けてください。
逆に、一度でも不正行為が疑われると、後のリスク負担は計り知れません。
正しい相続税申告によって、家族の財産を健全に守り、後々まで安心して暮らしていくための礎を築くことができます。
複雑さを理由に遠ざけず、しっかりと理解し、正しい知識を活かすことが重要です。
税理士法人羽賀・たちばなには、元国税専門官・元国税審判官の経験をもつ弁護士が在籍しています。
相続税の税務調査から、国税局の査察まで税務・法務の両面からトータル・ワンストップでサポートいたします。
相続税に絡むトラブルの法律相談をおこなっています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。