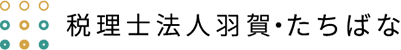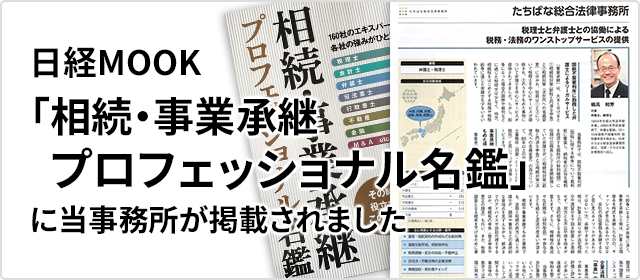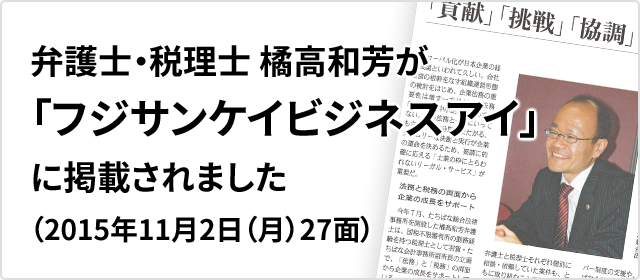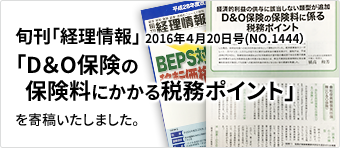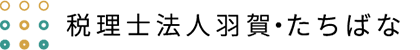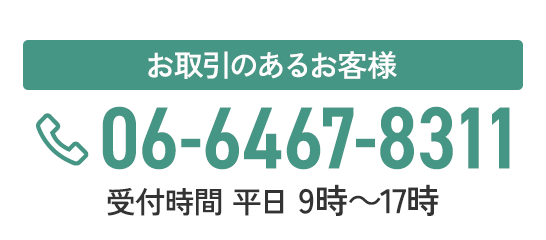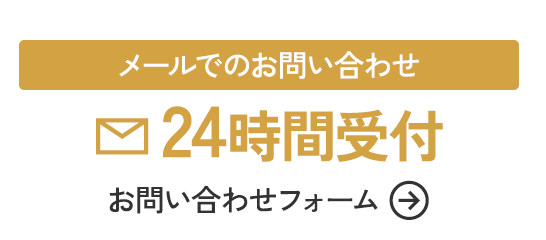税理士が「脱税ほう助」で刑事罰の対象になる場合。 予防策や対処法も解説。
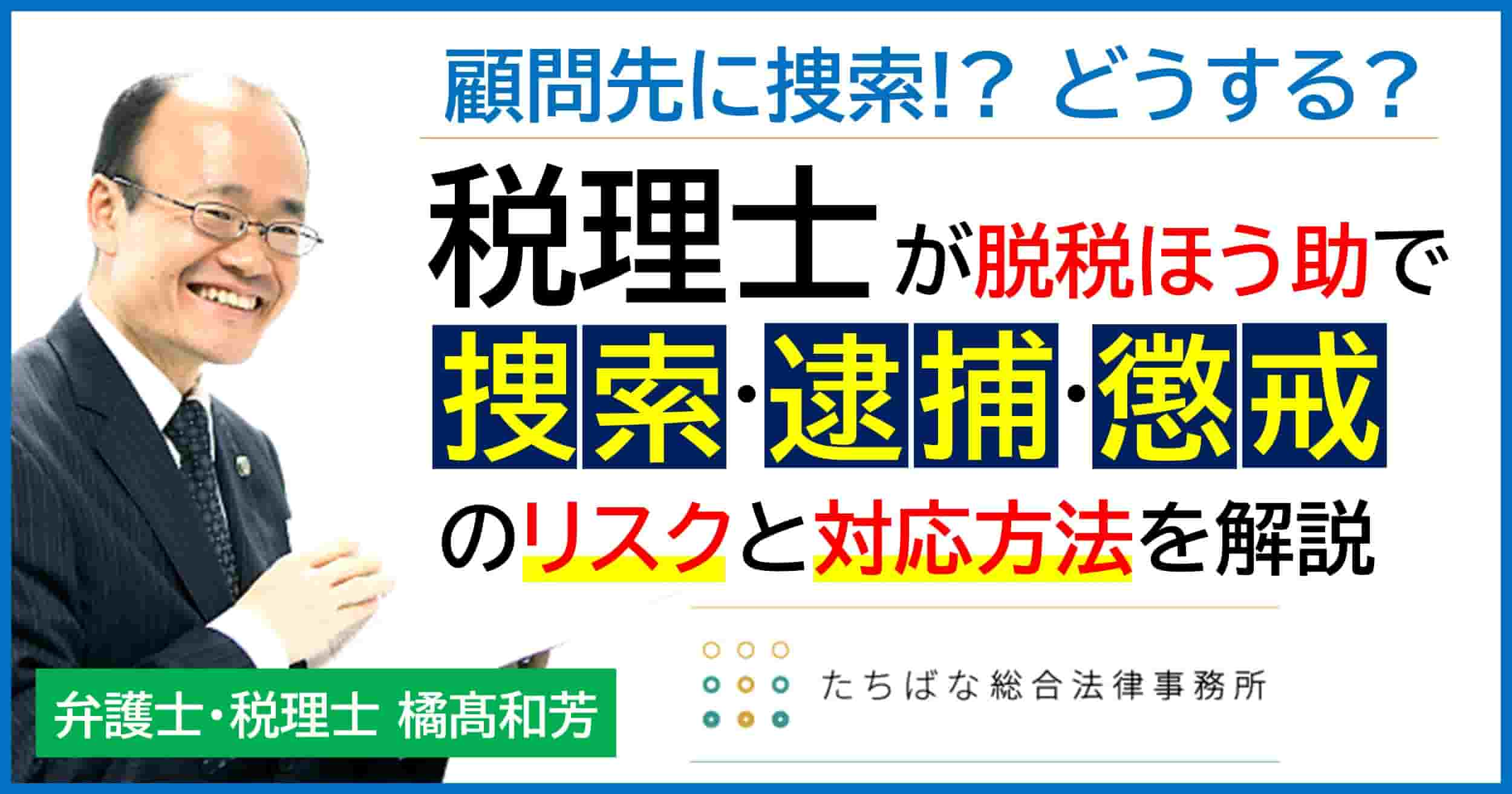

税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
たちばな総合法律事務所 代表弁護士 橘髙 和芳
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。

税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
たちばな総合法律事務所 弁護士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。
このコラムの要点(目次)
1.税理士の「脱税ほう助」
1-1.「ほう助」犯とは?
「ほう助」とは、漢字で表記すると、「幇助」で、いずれも「たすける」という意味を持ちます。
主犯である納税者が脱税し、会計士や税理士がそれを知りながら手助けした場合にほう助犯として処罰対象となります。
1-2.どのような場合「脱税ほう助」となるか
大雑把にいうと、①主犯である納税者が脱税犯として処罰対象になる(査察の捜査対象になる)ような②売上除外や架空経費計上などの実行行為を行うこと、③会計士や税理士がそれと知りながら、内容虚偽の申告書を作成・申告することとなります。
そのため、主犯である納税者が脱税犯として処罰対象となるほど所得金額を脱漏したか、脱税金額が多額であること(且つ逋脱の意思があること)を要します。
そして、会計士や税理士が内容虚偽と知りながら、申告書を作成・提出すると、「脱税ほう助」犯に当たる可能性が高まります(刑法62条1項)。
なお、会計士や税理士が脱税方法について指南したり唆したりしたら教唆犯(刑法61条)、共謀して主体的に脱税行為を行ったり脱税した税金を山分けしたら共同正犯となり(刑法60条)、主犯と同等の処罰対象となります。
2.関与先が「脱税」で捜査を受けたときの対応
2-1 納税者・依頼者とは別の弁護士を選任する必要
関与先や税理士事務所が脱税の捜査を受けたとき、弁護士に相談することが重要ですが、関与先と税理士事務所が同じ弁護士に弁護を依頼することはできません。
刑事事件では、「共犯」関係にある、外観上「共犯」関係にあるように見える場合、それぞれが自分の罪状を軽くするために他の共犯者に責任を押し付けるような供述をする傾向があることから、一人の弁護士が相談を受けると、あちら立てばこちら立たずの利益相反関係になるためです(さらに言うと、税理士法人の場合には、税理士法人と申告を担当した税理士個人との間にも利益相反の関係があります)。
そのため、税理士事務所は、関与先とは別に税理士を弁護する弁護人を探す必要があります。
関与先が弁護人を選任したからと安心していると、「税理士に助言を受けた脱税をした、助言を受けなかったら脱税なんてしない」などと言った供述調書のみが残ってしまう可能性があるためです。
2-2 顧問契約を継続するか、解消するか
捜索差押を受けたからと言って、関与先が有罪というわけでは全くありません。
そのため、顧問契約を解消せずに関与を継続するという判断も十分に合理的です。
他方、供述が相反する、巻き込みのリスクなどから、顧問契約を解消するという判断もまた十分に合理的です。
関与先の考え方の傾向、関与先からの相談内容、顧問契約に定めた義務の内容、予想される脱税の態様・脱税額などからの総合判断となり、弁護士と相談しながら決断することになります。
3.査察による会計士・税理士事務所に対する捜査の流れ
3-1.捜索差押とは?
捜索差押とは、捜査機関が証拠物・証拠書類を同意なく支配下に置くことを意味します。
3-2.税理士事務所もなぜ捜索差押の対象となるのか?
査察部門は、水面下で先行して捜査に着手をするか慎重に調査・選定を進めます。
そして、査察は、刑事事件化を目指すセクションですので、書類やメールの廃棄、口裏合わせといった証拠隠滅を回避するために、脱税したと思しき納税者の会社事務所、自宅、愛人宅は勿論のこと、申告書の作成・関与した税理士事務所にも捜索差押に臨みます。
捜索差押に入るまでは、納税者と会計士・税理士のどちら主体として脱税行為をしたか、それにより利益を得たか否かなどは分からないため、証拠保全(証拠隠滅予防)のために税理士事務所も捜索差押の対象となるのはある意味当然と言えます。
捜索差押を受けた会計士・税理士は、悪いことをしていないのに捜索差押を受けたことに、憤然とされたり、憮然とされたり、悄然とされたりしますが、この段階では「被疑者」ではなく、証拠保全のターゲットになったにとどまります。
3-3.捜索差押手続の流れ
あとで振り返ってはじめて気づいたという方が多いですが、前日などに見慣れない人がいたかもしれない人を事務所近くにいる場合があります。
これは、捜索差押に臨んでも、休業日に当たるかもしれないことや責任者の出勤時刻の確認と言う意味があります。
なお、休業日であっても、責任者である会計士・税理士がいなくても捜索差押手続は可能ですが、ターゲットとなる書類・メールがどこにあるかを一番よく知っている責任者である会計士・税理士にいたほうが、結果的に時間を節約することができる可能性があります。
捜索差押では、関係資料の探索と確認、差し押さえた書類の目録の作成という流れを取ります。
パソコン内の関係データ、メールについても対象となりますので、その選別作業の時間がかかります。
そのため、捜索差押は、9~10時に始まり、15~17時までかかることが多いです。
3-4.捜索差押後の捜査の有無(取調べと供述調書)
刑事事件としてみた場合、脱税で最も利益を受けるのは納税者・申告依頼者であることから、税理士は、「被疑者」よりも「証拠」・「参考人」としてとらえられる場合がほとんどです(脱税スキームを提案・主導していれば、「参考人」ではなく「正犯」となります。)。
そのため、捜索差押後に、事情を聴きたいと呼び出しを受けるか、受けるとして何回取調べを受けるかは、脱税への関与の深浅によります。
脱税に税理士が関与していると疑われる場合には日を置いて、「参考人」として取調べを受けて、質問応答録取書・供述調書を作成することになります。
質問としては、納税者・申告依頼者との話合いの状況、どちらが脱税を提案したか・受け身か・そもそも架空経費や売上除外を聞いていたか、脱税による利益の配分があったかなど事細かく質問されます。
ただし、税理士に有利なことは質問されませんので(例えば、「税理士が納税者・申告依頼者に対し売上や経費の確認をしたが、納税者・申告依頼者が売上除外や架空経費はないと確かに説明した」との供述は、納税者・申告依頼者に不利な事実ですが、結果的に税理士に有利な事実となりますが、取調官は、参考人に有利なように質問をするという意図は全くなく、単に事実関係を確認したいという意図にとどまります。)、有利な事実は積極的に供述する必要があります。
質問応答録取書・供述調書について、最後に読み聞かせられて、記憶に間違いが無ければ署名押印を求められます。
署名押印は、被疑者であれ、参考人であれ、被疑者・参考人の権利ですので、また、後日撤回はできず供述調書記載の事実があったと認定されてしまうので、少しでも記憶と違うところがあれば、訂正を求める必要があります。
また、税理士・会計士は、業務停止の懲戒処分を受ける可能性もありますので、慎重に供述することが非常に重要です。
3-5 どのような弁明をするべきか
刑事事件の取調べ肝要なことは、記憶通りのことを話す・書証物証に合致させること(曖昧な記憶で書証と矛盾する供述は厳禁)です。
また、主犯である関与先がどのような供述をするかの予測も考慮要素にはなります(「私は一切脱税に関与しておらず、税理士が勝手に内容虚偽の申告を提出しました。でも、脱税したお金を山分けしていず、顧問料も申告報酬は相場以下しか払っていません。」という不合理な供述であれば無視してもよいですが、「疑問に思って資料をメールで送って質問したところ、うまくやるから報酬を多めのもらいますとのメール返信が来た」と言う場合には上記メールの解釈や関与先とのその後のやり取りについて詳細に検討する必要があります)。
そのうえで、具体的には、①脱税幇助を知らないのか・知らないことに過失はないのか(関与者との契約に従った義務を履行しているが、専門家であれば通常疑問に思うような異常値に気づかなかったのか)、②真実の納税額は、脱税額とそれほど変わらないのか、③脱税に関与している認定されてしまう場合には、有利な情状の主張(懇意にしている知り合いから無理を言われて依頼された、依頼を断っても納税者がしつこく食い下がってきて真実の納税額に近づけるように説得を繰り返したなど)をしていくことになります。
3-6 弁明・供述の内容について、素人判断は禁物
査察官や検察官による取調べで、会計士・税理士にとってどのような内容が有利であるかなどについて、素人判断は非常に危険です。
そのため、例えば言換えを繰り返して徐々に「今から考えると、そうかもしれないです」→「専門家だから、当時売上脱漏をわかっていたと言われればそうかもしれません」(未必の故意)→「専門家なのでうすうす売上脱漏に気づいていました」(確定的故意)→「売上脱漏に気づいていましたが、そのまま申告書を出しました」(逋脱の意思)と、どんどん飛躍していくことがあります。
また、取調官である査察官や検察官は、あなたに有利になるように配慮することはなく、ただ事実を確認して起訴したいという一念で取り調べに当たります。
また、訂正を求めても「先生の言っていることは、文書で表現するとこうなるから」とか、「意味は同じだから」とか、訂正しても意味が同じ訂正になっていなかったりとかする場合もあります。
そのため、刑事事件と税務の内容や申告実務に詳しい専門家の助言を受けながら取調に臨む必要があり、供述調書への署名押印は慎重に判断する必要があります。
3-7.査察官の取調のみで終わるか、査察官と検察官の取調もあるか
脱税で捜査を受けた場合、全ての案件が査察官から検察官に事件送致されて裁判所に起訴されるわけではありません。
被疑者(多くは納税者・依頼者)の脱税事件が、検察官に事件送致されない場合には、税理士・会計士の取調は、査察官に対するのみとなります。
脱税事件が検察官に事件送致をされると、税理士・会計士の事件への関与度合いによりますが、税理士・会計士も検察庁に呼ばれて取調べを受け、調書(検察官面前調書)を作成することになります。
検察官面前調書は、刑事訴訟法で強い証拠力が認められているので、より慎重に供述する必要があります。
3-8 起訴・不起訴と刑事裁判
検察官は、捜査資料の一切から起訴・不起訴を判断します。
起訴されると、刑事裁判が開かれることになり、自認・自白事件では2回(1回目は1時間弱、2回目は判決言い渡しで10分弱ほど)、否認事件は多数回の公判手続が続くことになります。
3-9 有罪判決による税理士資格喪失
執行猶予付きであっても、有罪判決を受けると、欠格事由となり、執行猶予期間は税理士業務はできなくなります。
また、罰金であっても、罰金を完納してから3年間は欠格とされます。
そのため、税理士・会計士としては、不起訴処分を目指すことが非常に重要になります。
4 国税局による懲戒処分
4-1 不起訴でも懲戒処分はある
税理士・会計士は、不起訴であったとしても、国税局による懲戒処分を受ける可能性はあります。
刑事事件と行政処分は別手続のため、例えば自動車を運転して人を死傷させた場合、自動車運転過失致死傷罪で刑事事件として制裁を受け、自動車運転免許の取消処分で行政上の制裁を受けるというのと同じで、刑事事件と行政処分の両方を受ける、刑事事件化しないものの業務停止の行政処分を受ける、刑事も行政も処分を受けないという3通りの結論がありえます。
4-2 故意の場合の懲戒処分
税理士・会計士は、脱税幇助として起訴されれば、「故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は法第36条(脱税相談等の禁止)の規定に違反する行為」をしたものとして、懲戒処分を受け、6月以上1年以内の業務停止・税理士業務の禁止となります。
なお、脱税幇助として起訴されない場合でも、逋脱の意思とまで言えないまでも、故意があったとして、上記と同様の6月以上1年以内の業務停止・税理士業務の禁止の懲戒処分を受ける場合もあります
4-3 過失の場合の懲戒処分
相当の注意を怠って(つまり過失により)、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は法第36条の規定に違反する行為をしたとして、戒告又は1月以上1年以内の税理士業務の停止処分を受けることになります。
4-4 懲戒処分に当たっての考慮要素
懲戒処分するにあたっての考慮要素は、①行為の性質・態様・効果、②税理士の行為の前後の態度、③懲戒処分の処分歴、④他の税理士・社会に与える影響、⑤その他個別事情を考慮するとされています。や
はり、脱税行為の悪質性・脱税金額が1番の考慮要素となります。
ここでも書証物証に合致させつつ、記憶に合致する説明をすること、真実の納税額と脱税額との開差が小さいことの説明などの主張が重要となってきます。
5 普段からの備え、転ばぬ先の杖としての法律顧問の重要性
客商売として考えた場合、依頼者の要望に出来る限り応えるというのは重要なことです。
会計士・税理士は、納税者である依頼者から「節税」などの相談を受けることはよくあると思われ、「一定程度」の回答をすることは問題ありません。
しかしながら、一般の関与先の納税に係るコンプライアンス意識には、濃淡があり、固い解釈・事実認定で納税を希望される方から、これくらい(の脱税額)だったらばれませんよねと言う方、お金を払っているんだから税理士の方でうまく(?)やってほしいと言う方など様々です。
自分勝手な法に触れる脱税の相談をする関与先は、自己の利益を最優先するという考え方のため、税務調査や査察調査の際に責任転嫁をして自分の責任を軽く見せようとする傾向が強い印象があり、「会計士・税理士が違法と教えてくれなかった」とか、「会計士・税理士に言われたとおりに処理しただけで俺は悪くない」と責任転嫁する傾向が強い印象があります(刑事弁護の世界では「巻き込み」と表現され、「あるある」です。)。
また、脱漏所得金額、脱税金額が大きいときで、見解の相違、証拠評価・事実認定の相違では合理的に説明できない場合には、税理士・会計士が脱税ほう助「犯」となってしまい、資格を失ってしまいます。
そのため、関与先からしつこく脱税の相談を受けた場合の対応、どこで顧問契約解除の線引きをするかについて、弁護士と法律顧問契約をして、弁護士と日常的に相談をすることができることにするのが重要です。